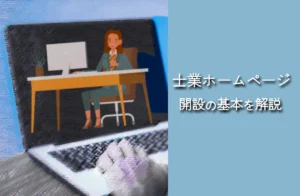酒類を販売するためには、国税庁の管轄である税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
この記事では、酒類販売免許の種類、取得条件、申請の流れ、必要書類を解説します。
これから酒類販売を始めたい方、事業に酒販を追加したい方はぜひ参考にしてください。
酒類販売免許とは?
酒類を継続的に販売するには、酒税法に基づき、酒類を販売する場所ごとに、その販売所の所在地の所轄税務署長へ「酒類販売免許」の申請を行い、免許を受ける必要があります。
したがって、複数の店舗で酒類を販売するには店舗ごとに免許を受けることが必要になります。
販売形態や対象者、販売場所などによって複数の種類に分かれており、適切な免許を取得する必要があります。
酒類販売免許の種類
酒類販売免許は大きく以下のように分類されます。
- 一般酒類小売業免許:実店舗で不特定多数の消費者に酒類を販売する場合
- 通信販売酒類小売業免許:インターネットやカタログなどを通じて消費者に酒類を販売する場合
- 特殊酒類小売業免許:自社の従業員や役員向けに酒類を販売する場合
- 酒類卸売業免許:他の事業者に対して酒類を販売する場合
一般酒類小売業免許
一般酒類小売業免許とは、販売場において、原則としてすべての品目の酒類を販売することができる酒類小売業免許のことです。
具体的には、酒屋さんやコンビニなど店舗を構えた販売所がお酒を販売する場合に必要となる免許であり、販売所ごとに免許を取得する必要があります。
一般酒類小売業免許では販売するお酒の種類に限定はないため、色々な種類のお酒を販売することが可能です。
通信販売酒類小売業免許
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどの通信手段を通じて、2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類を販売するための免許です。
具体的には、ECサイトで酒類を販売する場合などが該当します。
特殊酒類小売業免許
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者や料飲店等への販売を目的とせず、特殊な状況や関係者に対して酒類を販売するために必要な酒類販売業免許のことです。
具体的には、自社の役員や従業員に対し、酒類を社内販売する場合に必要となります。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者または酒類製造業者に対して酒類を販売することを認められる酒類販売免許です。
酒類卸売業免許は「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入酒類卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標酒類卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」の8種類に分類されています。
酒類販売免許の取得条件

酒類販売免許の取得には、以下のような要件を満たしている必要があります。
人的要件
酒類販売免許の人的要件は、申請者(個人または法人)の信用性や適格性を審査するものです。
具体的には以下の要件が挙げられます。
- 申請者が酒類製造免許若しくは酒類販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがないこと
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
- 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業法等の法律、刑法又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していることと
場所的要件
販売場所が法令に適合していること。賃貸物件である場合は使用許可が必要です。
場所的要件には以下のものがあります。
- 申請販売所が酒類の製造場、販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
- 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従業者の有無、代金決済の独立性、その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
経営基礎要件
経営基礎要件には、「免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと」があります。
具体的には以下の内容に該当していないことが必要です。
- 国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
需給調整要件(一般小売のみ)
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないことが必要となります。
具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。
酒類販売免許の申請の流れ

酒類販売業免許は、販売所所在地を管轄する「税務署の酒類指導官(酒類担当官)」が窓口になります。
個別具体的な相談がある場合、所轄税務署を担当する酒類指導官まで相談を行います。
酒類指導官が設置されている税務署及び担当税務署は、国税庁HP「酒税とお酒の免許についての相談窓口」で確認できます。
酒類販売には、酒類販売管理者を選任する必要があります。
酒類販売管理者には、酒類販売管理研修を受講することで選任することができます。
酒類販売業免許申請書及び申請時に提出すべき添付書類を準備し、管轄の税務署に提出します。
e-taxでの申請も可能です。
管轄の税務署において、申請順に審査が行われます。
標準処理期間(申請してから結果が出るまでの期間)は2ヶ月とされています。
免許が付与される場合、「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知後、税務署または金融機関等で登録免許税(免許1件につき3万円)を納付を行います。
「酒類販売業免許通知書」を受領後、酒類の販売開始可能となります。
一般酒類小売業免許申請に必要な書類
ここでは、一般酒類小売業免許に必要な書類を解説します。
- 酒類販売業免許申請書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し(法人の場合)
- 地方税の納税証明書
- 契約書等の写し
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(個人の場合には収支計算書等)
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 一般酒類小売業免許申請書チェック表
酒類販売免許申請を行政書士に依頼するメリット
酒類販売免許の申請は、提出書類が多く、準備に手間がかかります。
行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 書類作成・収集の代行
- 法令上のチェックやアドバイス
- 税務署とのやり取りをスムーズに代行
特に初めての申請者や法人設立と同時に免許取得を目指す方には、専門家のサポートが大きな安心材料になります。
まとめ
酒類販売免許は、販売方法や販売する対象によって種類が分かれています。
酒類販売免許の取得には、種類ごとの要件や書類、審査など多くの準備が必要です。
特に初めての方にとっては、書類作成や法律知識の面で戸惑うこともあるでしょう。
行政書士に相談することで、スムーズかつ確実な申請が可能になります。
「お酒を売りたい」と思ったそのときが、準備のスタートです。
正しい知識と計画的なステップを踏むことで、円滑に免許を取得することができるのです。