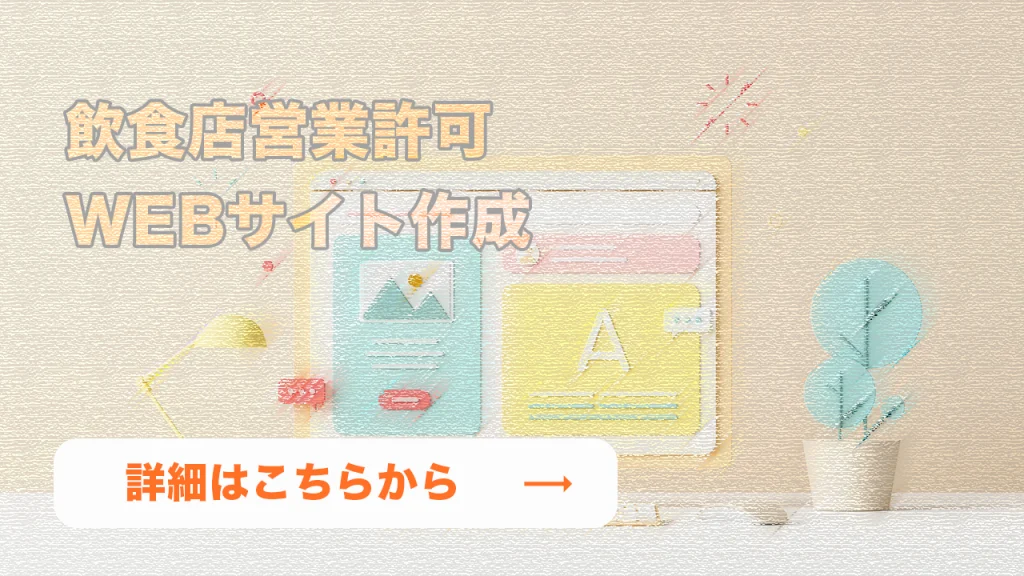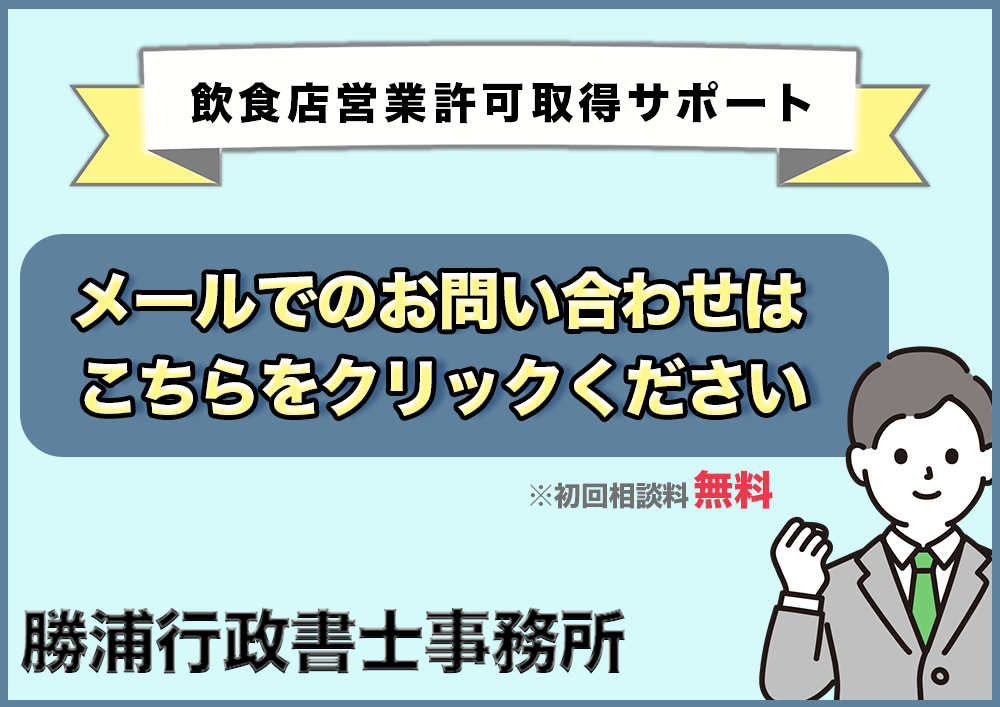飲食店を開業する際、「お酒を提供できるかどうか」は売上に大きな影響を与えるポイントです。
しかし、お酒の提供には必ずしも 酒類販売業免許 が必要というわけではなく、飲食店営業許可を持っていれば提供できるケースもあります。
本記事では、飲食店でお酒を提供する際に必要な許可や注意点を、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
飲食店でお酒を提供するのに必要な許可とは?
飲食店でお酒を提供する場合、まず基本となるのは 飲食店営業許可 です。
この許可を取得すれば、料理と一緒にお酒を提供することが可能になります。
飲食店営業許可(必須)
- 食品衛生法に基づき、保健所から取得する許可
- 店舗の衛生管理や厨房設備などが基準を満たしている必要あり
- この許可があれば、店内でお酒を「提供」することは可能
つまり、多くの飲食店(居酒屋、レストラン、バーなど)は、この許可を取得すればアルコール提供ができます。
酒類販売業免許(必要な場合のみ)
- 国税庁(税務署)の管轄
- 「店内での提供」ではなく、「販売して持ち帰りや通信販売をする」場合に必要
- ボトル販売をして持ち帰らせる、ネットでお酒を売る場合など
お酒を提供するには、「開栓した状態」か「開栓していない状態」かで、必要な許可要件が変わってきます。
開栓してない状態での販売には酒類販売業免許が必要になります。
お酒提供に関する注意点
(1)未成年者への提供禁止
- 20歳未満の方への提供は法律で禁止されています。
- 身分証の確認を怠ると、罰則や営業停止処分を受ける可能性があります。
(2)深夜営業に関する制限
- 午前0時以降にお酒をメインに提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出 が必要
- 居酒屋やバーを深夜まで営業するなら必ず確認が必要
(3)飲酒運転防止の配慮
- 飲酒運転につながる行為を助長しないことが求められます。
- 車で来店するお客様には、ノンアルコール飲料を案内するなどの工夫も重要です。
(4)広告・表示の注意
- 酒類の広告には過度な誇張や未成年を対象とする表現は禁止されています。
- チラシやWEBサイトを作る際も注意が必要です。
まとめ
飲食店でお酒を提供するために必要なのは、基本的には 飲食店営業許可 です。
ただし、深夜営業をする場合や販売を伴う場合には追加で届出・免許が必要となります。
店内での提供 → 飲食店営業許可でOK
深夜0時以降に営業 → 深夜酒類提供飲食店営業の届出
販売して持ち帰り・通信販売 → 酒類販売業免許
これらを正しく理解して準備することで、安心してお酒を提供できる飲食店経営が可能になります。
飲食店営業許可取得サポートは行政書士にお任せください
「飲食店を開業したいけど、許可申請の手続きが複雑でよく分からない…」
「保健所の審査に通るか不安…」
そんなお悩みをお持ちの方へ。
飲食店営業許可の申請手続きは、専門の行政書士にお任せください!
書類作成から申請代行までワンストップ対応!
スムーズな許可取得で開業準備を効率化!
保健所の基準に適合するためのアドバイスも提供!
飲食店開業を「手続き+集客」両面からサポート!
営業許可申請 × ホームページ制作をまとめてお任せ!
行政書士とWEBデザイナー、両方の資格と経験をもつ担当者が、飲食店開業をワンストップで支援します。
飲食店を始めるには、やることが山ほどあります。保健所への営業許可申請に加えて、店舗の準備、メニューの考案、スタッフの確保…。さらに、今はホームページやSNSを使った情報発信も必須です。
そこで、私は行政書士×WEBデザイナーという2つの専門性を活かして、開業手続きとホームページ制作を一括でサポートするパッケージサービスをご用意しました。
📞 初回相談無料!お気軽にお問い合わせください
詳細は下記画像からご確認ください