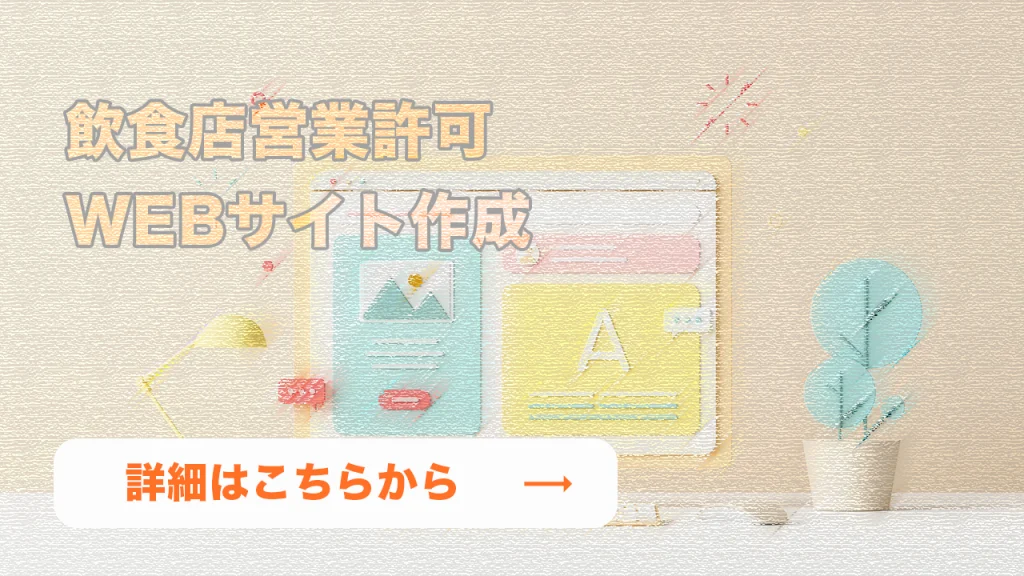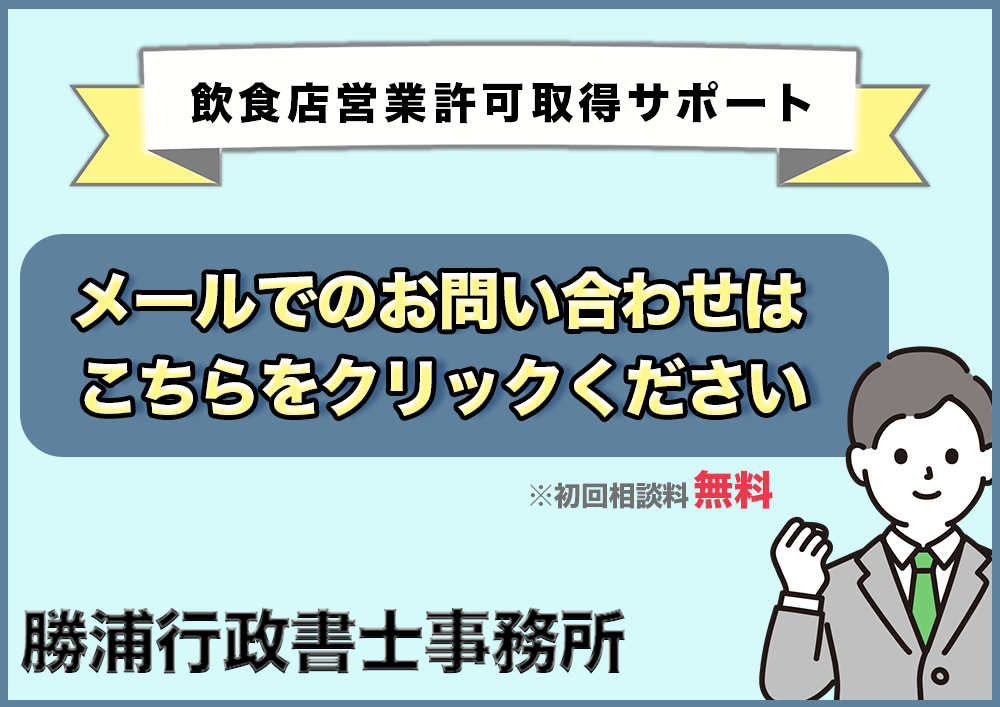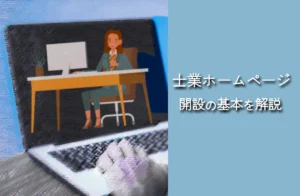飲食店を売却・譲渡するとき、「営業許可はそのまま引き継げるのでは?」と考える方は少なくありません。
以前は、食品衛生法において地位の承継の規定がないことから、事業譲渡が行われた際には、事業を譲渡する人は保健所へ廃業届の提出が必要であり、譲受人は事前に保健所へ新規の営業許可申請または営業届出が必要でした。
要は、同じ場所で同じ経営を行うとしても、経営者が変われば、「一旦事業を廃止して新しく営業許可を取得しなければならない」ということでした。
しかし、令和5年の食品衛生法の改正により、事業譲渡により営業者の地位を承継することができるようになりました。
この記事では、飲食店営業許可の事業譲渡について解説します。
従来のルールでは営業許可は引き継げなかった
飲食店を営業するには、保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。これは食品衛生法に基づくもので、「施設ごと」かつ「営業者ごと」に付与される許可です。
- 許可の対象:営業者(個人または法人)
- 許可の単位:施設単位(店舗ごとに許可が必要)
- 有効期間:原則5年間(自治体による)
つまり、同じ店舗でも経営者が変われば、その許可は失効します。
つまり、事業譲渡によって店舗を買い取ったとしても、買い手側が営業を継続するためには、保健所に対して新たな営業許可申請を行う必要があったのです。
令和5年の食品衛生法改正
以前は飲食店営業許可の譲渡はできませんでした。
しかし、令和5年の食品衛生法の改正により、飲食店営業許可の名義変更(譲渡)の手続きができるようになりました。
飲食店営業許可の事業許可の条件
事業譲渡を行い、新規に営業許可を申請する場合は、事業譲渡に伴う申請が必要となります。
飲食店営業許可の事業譲渡を行うには、以下の条件を満たす必要があります。
- 事業譲渡する営業が令和3年6月以降の許可を受けていること
- 施設設備に変更が無い
事業譲渡ができないケース
飲食店営業許可の事業譲渡を行う場合には、施設条件などに変更がないことが必要です。
以下の場合には許可の承継が認められない可能性があります。
- 店舗の一部のみを譲渡する場合
- 譲渡と同時に大規模な改装や営業内容の変更がある場合
事業譲渡の流れ
手順①:事前相談
まずは譲渡人・譲受人ともに保健所へ相談します。施設の図面や契約書の写しなどを持参し、承継可能かどうかを確認します。
手順②:届出書類の準備
保健所により異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 地位承継届出書
- 営業許可証(写し可)
- 事業譲渡契約書や覚書の写し
- 食品衛生責任者の資格証
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
手順③:地位承継届の提出
譲渡の効力発生日から30日以内に届出を行う必要があります(自治体により多少異なる)。
また、承継後の営業者名義で「許可証の書換え交付」を申請するケースもあります。
手順④:保健所による後日調査
届出完了後、保健所の職員が現地を訪れ、施設の衛生状態や設備の適合状況などを確認します。
手順⑤:許可証の受領
新許可証は、保健所に訪問し受け取る方法と、郵送で受け取る方法の2つの方法があります。
保健所に受け取りに行く方が早く受領することが可能です。
まとめ
令和5年12月13日から、飲食店の営業許可は一定条件のもとで譲渡や売却時に引き継ぐことが可能となりました。
令和5年の食品衛生法の改正からこの手続きが可能となったため、知らなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
飲食店営業許可の地位の承継(事業承継)を行うことで、以前までの廃業届・新規許可の取得よりも、手続きが楽になり、営業を停止している期間も短くできるようになります。
とはいえ、制度の適用には要件の確認と適切な手続きが必要不可欠です。
事業譲渡や店舗売却を検討されている方は、早い段階で保健所や専門家に相談し、スムーズな承継を目指しましょう。
飲食店開業を「手続き+集客」両面からサポート!
営業許可申請 × ホームページ制作をまとめてお任せ!
行政書士とWEBデザイナー、両方の資格と経験をもつ担当者が、飲食店開業をワンストップで支援します。
飲食店を始めるには、やることが山ほどあります。保健所への営業許可申請に加えて、店舗の準備、メニューの考案、スタッフの確保…。さらに、今はホームページやSNSを使った情報発信も必須です。
そこで、私は行政書士×WEBデザイナーという2つの専門性を活かして、開業手続きとホームページ制作を一括でサポートするパッケージサービスをご用意しました。
📞 初回相談無料!お気軽にお問い合わせください
詳細は下記画像からご確認ください