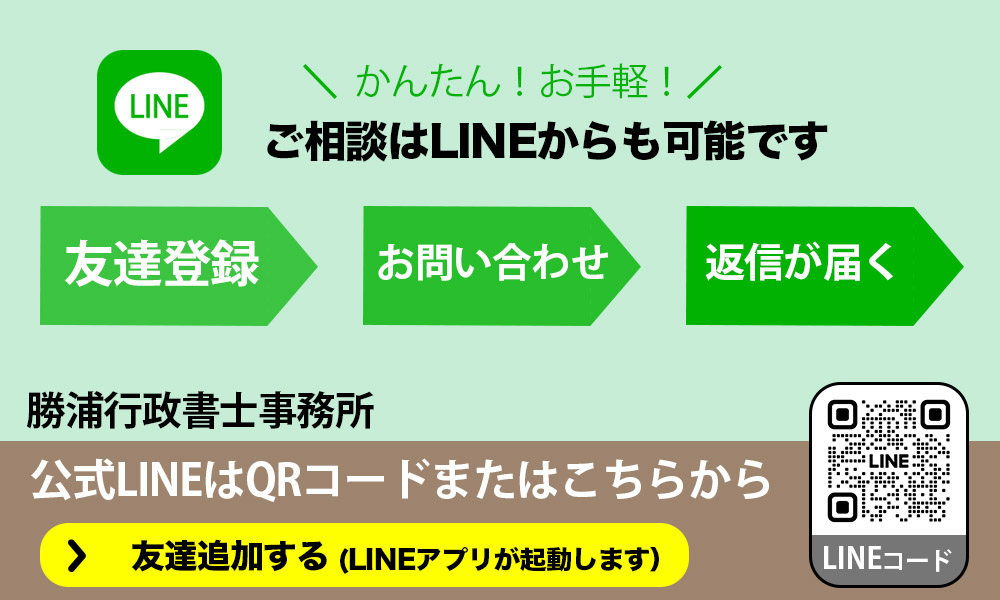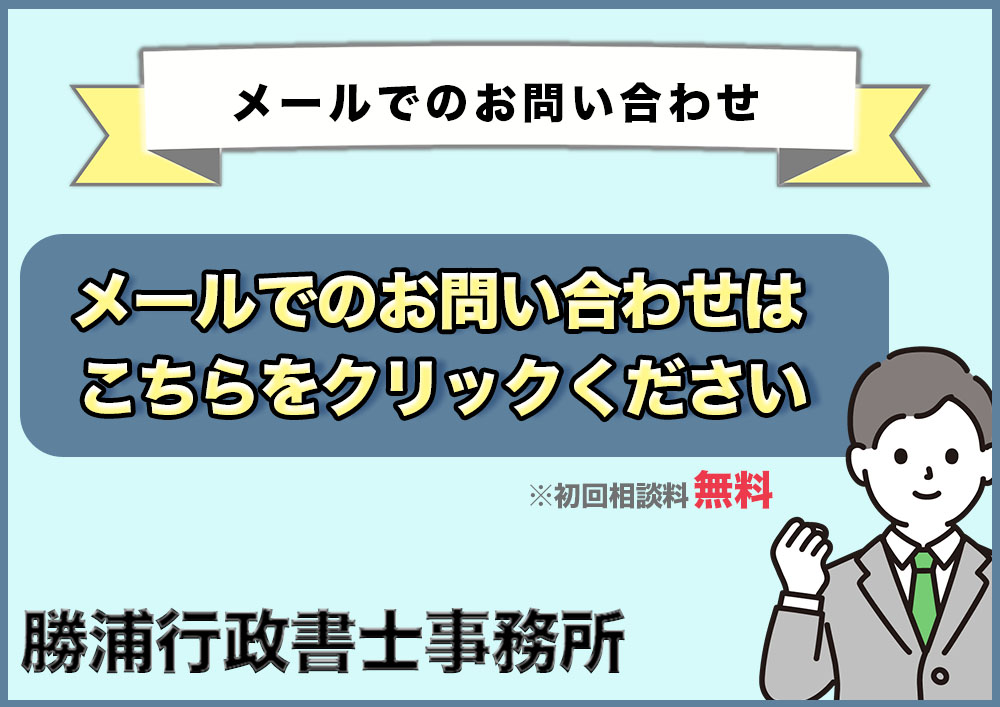『将来は居酒屋を開きたいなぁ』と思っている方も多いことでしょう。
居酒屋を開業することは、夢を実現する素晴らしい挑戦です。
しかし当然ながら、”思い立ったが吉日”で居酒屋を開業できるものではありません。
事前に計画を立て、準備をしっかりと行うことが非常に大切です。
居酒屋を開業する際には、さまざまな許可や届出が必要です。
これらの手続きを適切に行わないと、営業ができなかったり、営業開始できても営業停止命令を受ける可能性があります。
本記事では、居酒屋開業に必要な許可申請について詳しく解説します。
居酒屋開業に必要な資格・条件
居酒屋を開業するために必要となる資格や届出には、以下のものがあります。
- 飲食店営業許可
- 食品衛生責任者の資格
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届(条件により必要)
- 防火対象物使用開始届(ほとんどの場合必要)
- 防火管理者の資格(条件により必要)
飲食店営業許可
居酒屋を含めた飲食店を営業するためには、管轄の保健所に”飲食店営業許可”の申請を行い、許可を取得する必要があります。
この飲食店営業許可を取得するのに、かならず必要となる資格が「食品衛生責任者」で、条件によって必要となるのが「防火管理者」です。
防火管理者は、収容人数が店舗スタッフを含めて30名以上の店舗(客席の数ではありません)の場合、選任する必要があります。
飲食店営業許可は申請してから許可が下りるまでに2〜3週間程度かかります。
防火管理者は1日〜2日で取得できますが、講習を開催していない期間は取ることができませんので、開業予定日に合わせて取得できているようにスケジュールの確認が必要です。
飲食店営業許可については過去記事にて詳しく解説しています。ご参照ください
食品衛生責任者の資格
食品衛生責任者は店舗ごとに1名必要となります。
食品衛生責任者の資格を取得するには、養成講習会を受講する必要があります。
また、次の資格を持っている方は養成講習会を受講しなくても食品衛生責任者の資格を得ることができます。
- 栄養士・調理師・製菓衛生師の資格を持っている
- 食品衛生管理者・食品衛生監視員となる資格を持っているなど
その他にも、「管理栄養士」や「船舶調理師」などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
所持している資格が食品衛生責任者として認められるかは「職員衛生責任者の手続き(堺市)」を参照ください。
「栄養士」や「調理師」の資格を持っていなくても、”養成講習会”を受講し、試験に合格すれば食品衛生責任者の資格を得ることができます。
養成講習会は試験を含めて6時間ですので、講習を受講し、試験に合格すれば1日で職員衛生責任者の資格を取ることが可能です。
食品衛生責任者養成講習は、学歴や職歴に関係なく受講することができますが、自治体によっては年齢制限が定めれていることがありますので、事前に確認が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
深夜酒類提供飲食店営業開始届とは、午前0時から午前6時(夜中から早朝)にお酒の提供を行う際に必要な届出になります。
しかし、すべての飲食店において届出が必要なわけではなく、「お酒の提供をメインとする飲食店」が0時から6時までの間にお酒を提供する場合に届出が必要となります。
居酒屋はお酒の提供をメインとする飲食店ですので、0時から6時の間も営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の手続きが必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業については過去記事で詳しく解説しています。ご参照ください。
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届とは、建物やその一部を新たに使用する際、管轄の消防署に提出する届出書です。
対象となる建物は、「個人住宅以外の防火対象物(建物)のすべて」です。
届出必要となるケースには、以下のものがあります。
- 事業の開始
- テナントの変更
- 所有者の変更
- 増改築・間仕切りの変更
内装工事や間仕切り工事を行う場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」も必要となります。
居酒屋を開業する場合、内装工事をしなくても「防火対象物使用開始届」が必要、内装工事をする場合には、「防火対象物の工事等計画の届出」も併せて必要となります。
防火管理者の資格
収容人数が30名以上となる店舗には、防火管理者の選任が義務付けられています(消防法第8条)
収容人数というのは、従業員も含めた数になり、客席の数ではないため注意が必要です。
例えば、客席の数が25席で従業員が6名いる場合、防火管理者の選任が必要となります。
防火管理者には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類があります。
店舗の延べ面積が300m2未満であれば「乙種防火管理者」、300m2を超える場合には「甲種防火管理者」の資格が必要となります。
防火管理者の選任が必要な飲食店で防火管理者の選任をしていない場合、消防法第42条に基づき、「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となりますので、防火管理者の選任義務に該当するかは確認しましょう。
出店場所の条件

居酒屋を出店する上で気をつけたいのが出店予定地の用途地域です。
日本の土地は、都市計画法で13種類の地域(用途地域)に分け、建築制限を定めています。
住居専用地域には、基本的には事務所や店舗を建てることはできません。(店舗兼住宅であれば可)
また、住居系用途地域では、原則として深夜営業はできないため、深夜(0時から6時)まで営業しようと考えているなら、深夜営業が可能な場所を選ぶ必要があります。
物件を決める前に必ずその場所の用途地域は確認しなければいけません。
物件を契約した後で、飲食店営業許可が下りない用途地域だった場合、取り返しがつかない事態になってしまいます。
◆ 商業地域
◆ 近隣商業地域
◆ 工業地域
◆ 準工業地域
用途地域は各自治体に確認するほか、自治体のHPや用途地域マップにおいても確認できます。
(参考:大阪市用途地域)
準備から開業までの流れ
一般的な開業準備から開業までの許可や届出の流れは以下のようになります。
どのような居酒屋を開業するか明確にするため、事業計画を作成します。
融資を受けることが必要であれば、その準備も必要です。
出店可能な用途地域であるか必ずチェックします。
深夜営業も視野に入れているなら住居系用途地域はNG
飲食店営業許可の基準を満たさなければなりません。
内装工事を行う場合、「防火対象物の工事等計画の届出」が必要
飲食店営業許可・防火対象物使用開始届・深夜種類販売営業開始届など
営業開始
事業計画の策定
「お店のコンセプトは何か」「ターゲット層を決める」など、事業計画の策定には多くの時間と労力が必要です。
◆ ターゲット層を決める(サラリーマン向け、若者向けなど)
◆ コンセプトを明確にする(和風、モダン、創作料理など)
◆ 商圏調査を行う
◆ 収支計画を立てる(売上目標、費用の試算、損益分岐点)
◆ 競合分析を行う(同エリアの居酒屋を調査)
金融機関からの融資を受ける場合、事業計画書が必要になりますので、現実的なビジョンを見据えてじっくりと検討することが必要です。
自己資金だけで開業する場合でも、事業計画書を策定しコンセプトを明確にすることにより、開業後の
まとめ
居酒屋開業には、コンセプト決定から資金調達、内装工事、スタッフ採用、集客戦略など、多くのステップがあります。
これらのことを行いながら必要な許可申請や届出、保健所などの関係機関との調整を行うことは本当に労力がいることです。
開業の準備に専念できるよう、必要な許可や届出の手続きは許認可手続きの専門家である行政書士にお任せください。
居酒屋開業の許可申請・届出サポートは勝浦行政書士事務所にお任せください
居酒屋を開店するには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
届出に必要な図面の作成は多くの手間と時間を必要とします。
手続きの不備や遅れが原因で開業スケジュールが狂ってしまうことも…。
そんなお悩みは、行政書士にお任せください!
許認可手続きの専門家が、スムーズかつ確実に開業準備をサポートします。
- 飲食店営業許可の申請サポート
- 必要書類の作成・提出代行
- 保健所や消防署との調整代行
- 深夜酒類提供飲食店営業届の提出支援
開業準備に専念できるよう、複雑な手続きを丸ごとお手伝いいたします!
まずはお気軽にご相談ください。