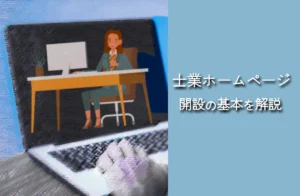近年、ECサイトを通じて様々な商品が販売されていますが、その中でも注目を集めているのが「酒類の通信販売」です。
クラフトビールや地酒、輸入ワインなど、個性豊かな酒類商品をオンラインで販売するビジネスは、少ない初期投資で始められる魅力的なビジネスモデルの一つです。
しかし、酒類を販売するには「酒類販売業免許」が必要となります。
特に、消費者に直接配送する形式の販売を行うには、「通信販売酒類小売業免許」の取得が必須です。
この記事では、通信販売酒類小売業免許を取得するためのポイントや注意点について詳しく解説していきます。
通信販売酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどを通じて、消費者に酒類を直接販売・配送する事業者が取得しなければならない免許です。
通信販売酒類小売業免許は、「2都道府県以上の広域な地域の消費者を対象とする通信販売」を行う場合に免許が必要となります。
したがって、同一都道府県で通信販売を行う場合には「通信販売酒類小売業免許」ではなくても、「一般酒類小売業免許」で販売することが可能です。
たとえば、大阪府堺市で一般酒類小売業免許を取得し販売所を経営している会社が、大阪府のお客さん向けにインターネットやカタログなどを通じた通信販売を行う場合、「通信販売酒類小売業免許」を新たに申請しなくても通信販売を行うことができます。
この免許は、国税庁の管轄である各地の税務署に申請することで取得できます。
一般的な小売店での酒類販売とは異なり、通信販売には特有の規制や条件があります。たとえば、20歳未満の者に対する販売の防止措置、販売方法の明示、適切な配送管理などが求められます。
販売は日本国内の消費者に対してのみ
「通信販売酒類小売業免許」に基づいて販売できるのは、日本国内の消費者に対してのみです。
この免許では、国外に住む個人や法人への酒類の販売・発送は認められていません。
一方で、海外の消費者(外国に居住する個人や海外法人など)に対して酒類を販売し、輸出することを希望する場合には、「輸出酒類卸売業免許」の取得が必要になります。この免許を取得することで、合法的に酒類を海外市場へ販売・輸出することが可能となります。
販売できるお酒の酒類
「通信販売酒類小売業免許」で販売できるお酒の酒類(販売品目)は、以下の条件に該当する酒類に限ります。
- 輸入酒類
- 国産酒類のうち、カタログ等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
- 地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品に限る)を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、どんなお酒でも取り扱うことができるというわけではありません。大手国産メーカーのお酒は取り扱うことはできません。
通信販売酒類小売業免許で販売できる国産メーカーのお酒は限定されます。
国産酒類は、「年間の課税移出数量が品目ごとに全て3,000kℓ未満である酒類製造者(メーカー)が製造する酒類」であれば通信販売することが可能です。
要は、大手国産メーカー(年間の課税移出数量が3,000kℓ以上のメーカー)が製造している酒類を通信販売することはできないということです。
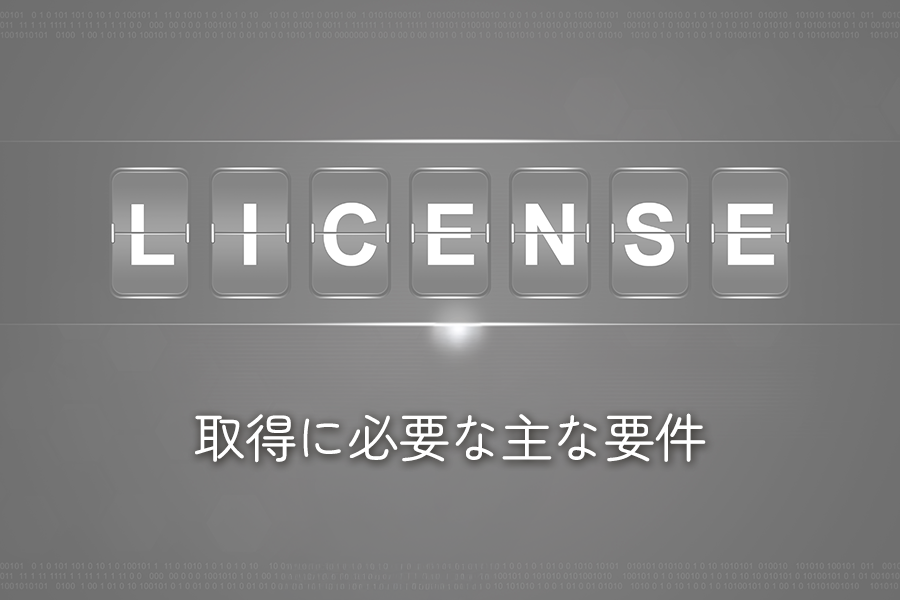
取得に必要な主な要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
経営基盤の安定性
申請者が事業を継続的に行うことができる財務基盤を有しているかが審査されます。過去の赤字や税金滞納の履歴がある場合は、不許可となる可能性があります。
具体的には以下の要件に当てはまらない必要があります。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
- 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
販売計画の適切性
酒類販売免許の取得には事業計画書や収支計画書の作成が必要となります。
酒類免許の取得申請では、通常の事業計画所とは違い、酒税法を盛り込んだ内容での事業計画書を作成する必要があります。
事業計画書は酒類販売免許申請の専用書式で作成します。
酒類の年間・月間の予定販売量や販売額、設備や人員の費用などを事前に計画しなければなりません。
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類の販売業務を開始するときまでに、「酒類販売管理者」を選任しなければなりません。
酒類販売管理者に選任されるには酒類販売管理者研修を受講する必要があります。
酒類販売管理者研修の詳細や研修機関は「国税庁のHP」で確認することができます。
酒類販売管理者を選任しなかった場合には、50 万円以下の罰金に処されることになります。
保管場所の適法性
通信販売を行う酒類小売業が酒類を保管する場所には、営業所内のスペースや酒税法に基づく蔵置所(ぞうちどころ)などがあります。
お酒を営業所外部の保管場所に置く場合には、蔵置所設置報告書を管轄の税務署に申請する必要があります。
免許取得の流れ
酒類販売業免許は、販売所所在地を管轄する「税務署の酒類指導官(酒類担当官)」が窓口になります。
個別具体的な相談がある場合、所轄税務署を担当する酒類指導官まで相談を行います。
酒類指導官が設置されている税務署及び担当税務署は、国税庁HP「酒税とお酒の免許についての相談窓口」で確認できます。
酒類販売には、酒類販売管理者を選任する必要があります。
酒類販売管理者には、酒類販売管理研修を受講することで選任することができます。
酒類販売業免許申請書及び申請時に提出すべき添付書類を準備し、管轄の税務署に提出します。
e-taxでの申請も可能です。
管轄の税務署において、申請順に審査が行われます。
標準処理期間(申請してから結果が出るまでの期間)は2ヶ月とされています。
免許が付与される場合、「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」により通知後、税務署または金融機関等で登録免許税(免許1件につき3万円)を納付を行います。
「酒類販売業免許通知書」を受領後、酒類の販売開始可能となります。
免許取得後の注意点

酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されておりますので注意が必要です。
記帳義務
酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し以下の事項を帳簿に記載しなければならないと定められています。
-
仕入れに関する事項
- 仕入数量
- 仕入価格
- 仕入年月日
- 仕入先の住所及び氏名又は名称
-
販売に関する事項
- 販売数量
- 販売価格
- 販売年月日
- 販売先の住所及び氏名又は名称
酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
申告義務
酒類販売業者は、以下の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。
e-Tax により申告を行うことも可能です。
【毎年度報告が必要なもの】
| 報告事項 | 報告期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量 | 翌年度の4月30日まで | 酒類の販売数量等報告書 |
【次の事由が生じる都度、申告等を要するもの】
| 事由 | 申告等事項 | 申告等期限 |
|---|---|---|
| 住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合 | 異動があった住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称 | 直ちに(事由が生じた後、すぐに) |
| 酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合 | 酒類の販売業を休止する旨又は再開する旨 | 遅滞なく |
| 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合 | 酒類の貯蔵のための 倉庫等を設ける旨又はその倉庫を廃止する旨 | あらかじめ |
| 税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合) | 酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称等 | 別途定める日まで |
まとめ
通信販売でお酒を販売するには、単にECサイトを作るだけではなく、「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。手続きには一定の期間と労力がかかるため、事前準備をしっかりと行うことが成功の鍵です。
もし、申請手続きや要件について不安がある場合は、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。