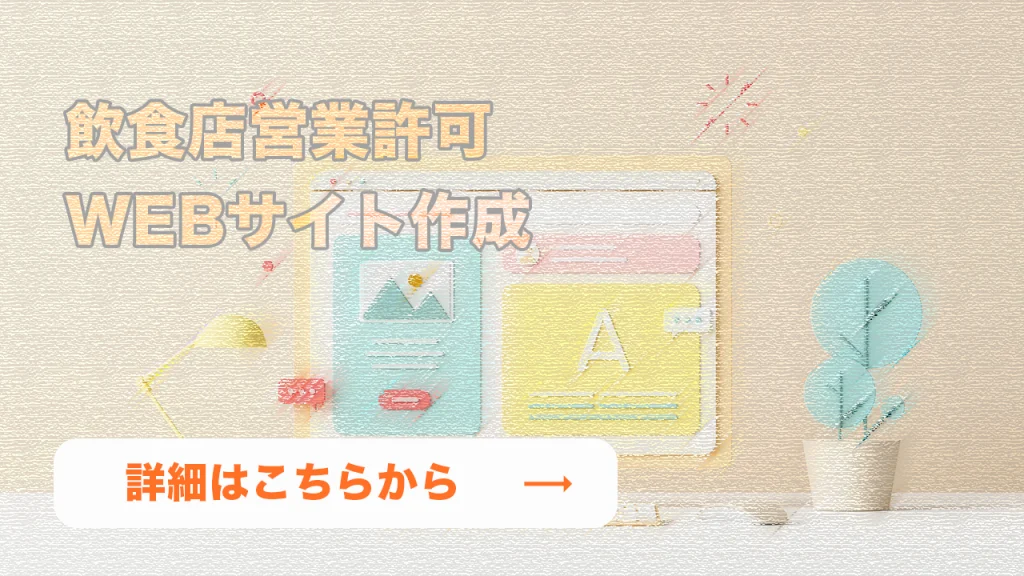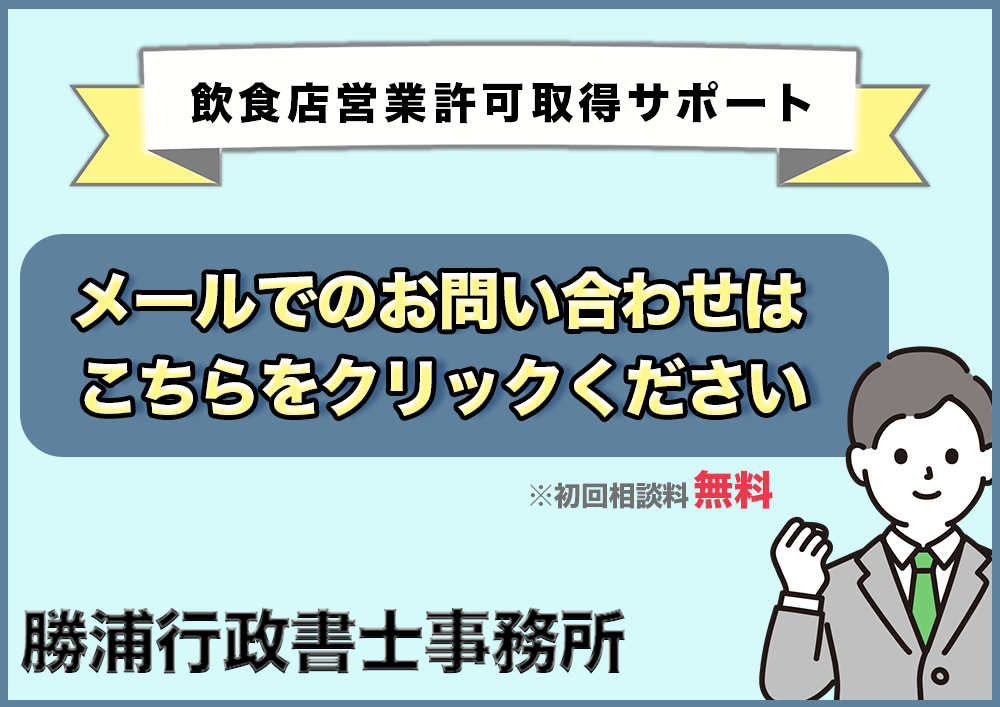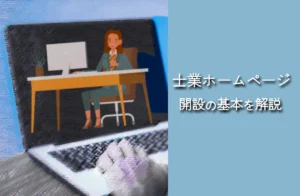「自宅でカフェを開業したい」
そんな夢を持つ方は年々増えています。自宅の一部をおしゃれな空間に改装し、自分のペースで好きなコーヒーや軽食を提供する——そんな働き方は、多くの人にとって理想的です。
しかし、自宅カフェを始めるには、単に料理や接客のスキルだけではなく、法律の知識や設備の整備、地域のルールにも対応する必要があります。
この記事では、自宅カフェを開業するにあたって「事前に知っておくべき法律や準備項目」を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
自宅カフェの特徴とメリット・デメリット
自宅カフェのメリットには以下のようなものがあります。
- 初期費用を抑えられる
- 家事や育児との両立がしやすい
- 通勤の必要がない
- オリジナルの空間を作れる
一方で、自宅カフェには以下のようなデメリットも考えられます。
- 住宅街での営業には近隣とのトラブルリスク
- 店舗としてのスペースに限りがある
- 生活スペースとの線引きが難しい場合も
飲食店を開業するための初期投資の平均額は1000万円とも言われています。
自宅でカフェを開業することは、店舗のテナント料金などが抑えられる分、初期投資額を減らすことができます。
一方で、近隣トラブルの原因になったり、店舗の広さに制限があるなどのデメリットになる要素もあります。
自宅カフェを始めるには「営業許可」が必要

飲食店を始めるためには、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
この記事を読んでいただいている方の中には、「喫茶店営業許可」という言葉を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれませんが、「喫茶店営業許可」は2021年の食品衛生法の改正により、「飲食店営業許可」の中に組み込まれました。
カフェを始めるためは、独立店舗型でも、自宅併設型でも「飲食店営業許可」の取得が必要となります。
自宅の用途地域を最初に確認
飲食店を開業するにあたって、店舗を設置する場所の用途地域は非常に重要となります。
| 用途地域 | 飲食店店舗出店 | 備考 |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 | △ | 店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のもののみ可 |
| 第2種低層住居専用地域 | △ | 店舗兼住宅で、店舗床面積が50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1未満のものは可。 2階以下で、かつ店舗等の床面積が150㎡以下であれば喫茶店を出店・開業することが可能。 |
| 第1種中高層住居専用地域 | ○ | 店舗等の床面積が500㎡以下で、かつ2階以下であれば飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 第2種中高層住居専用地域 | ○ | 1500㎡以下で2階以下なら可。第一種中高層住居専用地域よりも、規模の大きな飲食店でも可能。 |
| 第1種住居地域 | ○ | ほぼ制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 第2種住居地域 | ○ | ほぼ制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 準住居地域 | ○ | ほぼ制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 田園住居地域 | △ | 店舗等の床面積が500㎡以下で、かつ2階以下であれば、その地域で生産された農産物を使用する場合は、農産物直売所(店舗)や飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 近隣商業地域 | ○ | 制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 準工業地域 | ○ | 制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 工業地域 | ○ | 制限なく飲食店を出店・開業することが可能。 |
| 工業専用地域 | × | 飲食店を開業することはできません |
用途地域によって、店舗の広さ制限が変わってきますので、『自宅でカフェを始めたい』と思ったら、まず最初に自宅の用途地域を確認する必要があります。
独立店舗型の飲食店は、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では開業することができません。
しかし、自宅カフェの場合、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域でも始めることが可能です。
自宅カフェを始めるための設備要件
自宅でカフェを始める場合にも「飲食店営業許可」を取得しなければならず、設備要件も自宅のある自治体の飲食店営業許可設備要件をクリアしなければなりません。
-
大阪府の場合の飲食店営業許可設備要件
- 洗浄設備
- 給水設備
- 手洗い設備
- 食器等保管設備
- 調理場の区画
- 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
- トイレ・更衣場所
自宅カフェの場合、生活空間と営業空間が明確に区分されていることが必要となります。
「自宅と店舗の出入り口が同じ」などは基本認められません。
自宅で飲食店営業許可を取得する場合、調理は自宅の台所で行うことはできず、調理場は自宅の台所と分ける必要があります。
「1階が店舗で2階が自宅」や「1階の1区画を店舗にする」などの形態に関わらず、自宅の台所とは別に店舗側にも調理場を設置しなければならないということです。
この設備要件は、一般の飲食店を開業するための設備要件とさほど変わりません。
一方で、一般の飲食店とカフェなどの喫茶店では、設備基準が食品衛生法施行規則において多少異なるものがあります。
床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあつては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
床面及び内壁にあっては、取り扱う食品や営業の形態を踏まえ、食品衛生上支障がないと認められる場合は、不浸透性材料以外の材料を使用することができる。
上記は一部の例ですが、カフェの開業では、一般の飲食店と設備基準が異なる場合がありますので、管轄の保健所に確認するようにしましょう。
自宅カフェに必要なその他の届出・手続き
自宅カフェを開業するには以下の手続きが必要となります。
- 飲食店営業許可の取得
- 食品衛生責任者の設置
- 開業の届出
- 防火管理者の設置(必要な場合)
自宅でカフェを開業するには、「飲食店営業許可」と「食品衛生責任者の設置」は必須となります。
「防火管理者の設置」は、従業員を含めた収容人数が30人以上となる規模のお店に設置が必要となるため、条件に該当しなければ、設置の必要はありません。
開業届は管轄の税務署に届出を行い、。個人事業としてカフェをオープンする場合に必要となります。
法人化して事業を行う場合は、法人設立を行う必要があります。
自宅カフェ開業のための事前準備チェックリスト
| 項目 | 内容 | 完了チェック |
|---|---|---|
| 物件の確認 | 用途地域・建築基準法の確認 | □ |
| 設備の整備 | シンク・換気設備・冷蔵庫など | □ |
| 許可の取得 | 飲食店営業許可・食品衛生責任者の取得 | □ |
| 生活スペースとの分離 | 店舗空間の明確化 | □ |
| 税務手続き | 開業届・青色申告申請 | □ |
| 近隣への配慮 | 騒音・駐車場トラブル対策 | □ |
まとめ
自宅カフェは、自由な働き方やライフスタイルの実現として魅力的ですが、法令遵守や設備要件、地域との共存など、しっかりとした準備が求められます。
特に初めて飲食店を始める方にとって、許可申請や地域ルールの確認は複雑に感じるかもしれません。
行政書士などの専門家に相談することで、申請ミスや無駄な出費を避け、スムーズな開業を実現できます。
飲食店開業を「手続き+集客」両面からサポート!
営業許可申請 × ホームページ制作をまとめてお任せ!
行政書士とWEBデザイナー、両方の資格と経験をもつ担当者が、飲食店開業をワンストップで支援します。
飲食店を始めるには、やることが山ほどあります。保健所への営業許可申請に加えて、店舗の準備、メニューの考案、スタッフの確保…。さらに、今はホームページやSNSを使った情報発信も必須です。
そこで、私は行政書士×WEBデザイナーという2つの専門性を活かして、開業手続きとホームページ制作を一括でサポートするパッケージサービスをご用意しました。
📞 初回相談無料!お気軽にお問い合わせください
詳細は下記画像からご確認ください