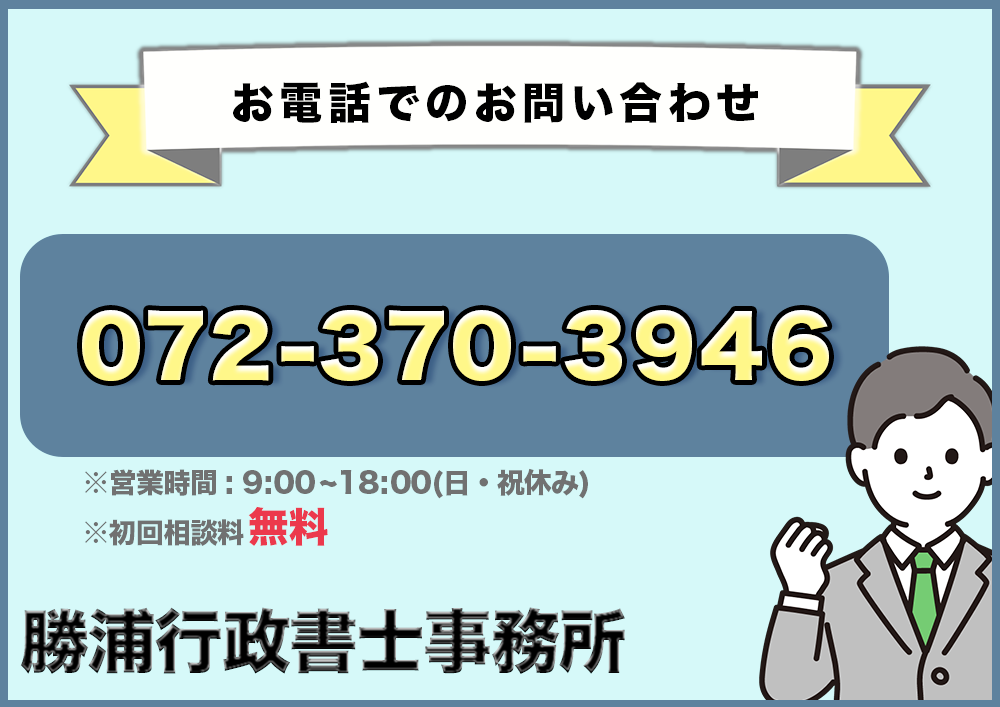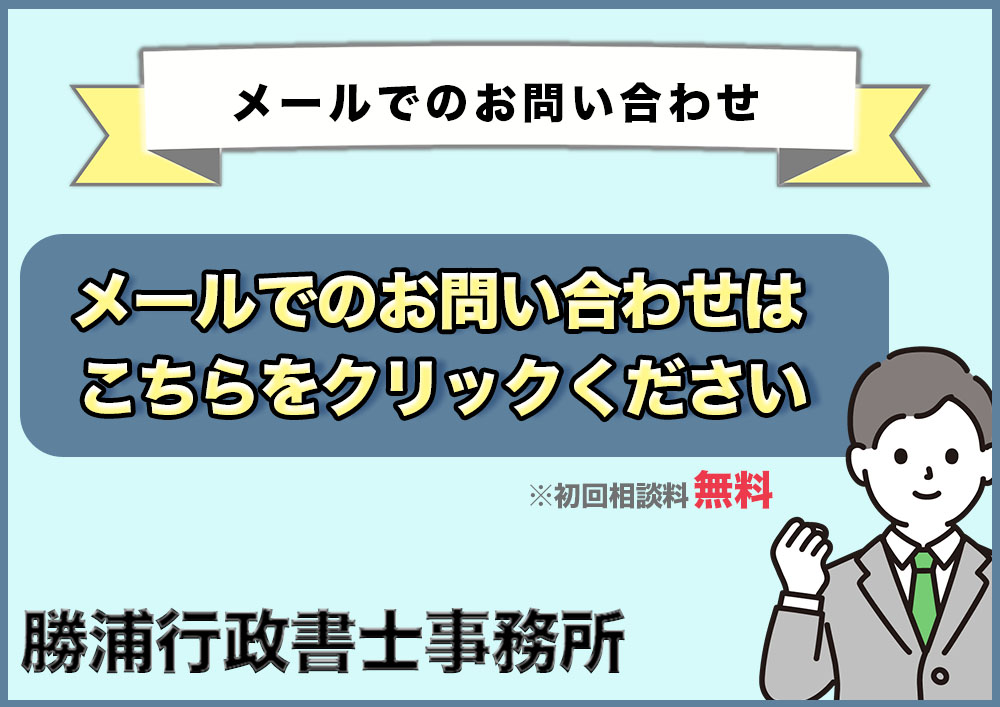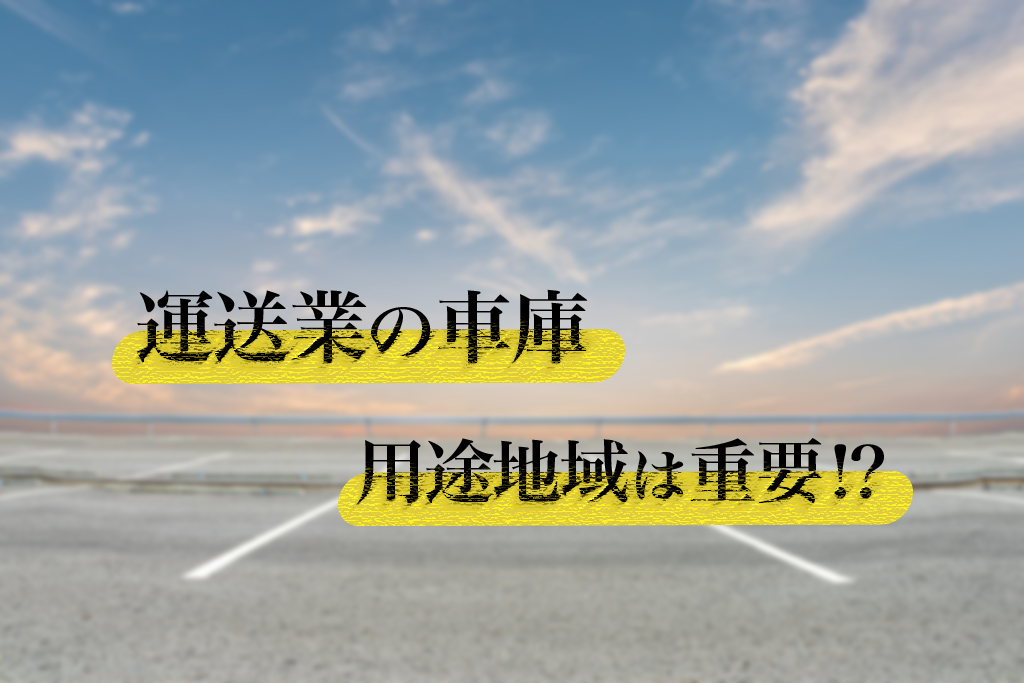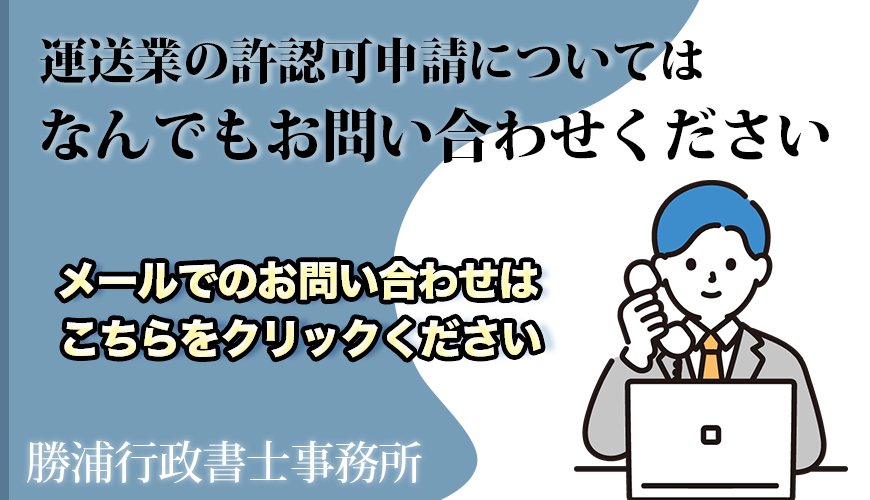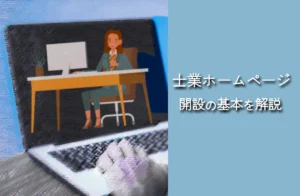運送業を始めるにあたって、「車庫の確保」は欠かせない重要なステップです。
しかし、単に土地があればよいというわけではなく、その土地がどの「用途地域」に属しているかによって、運送業の車庫として使えるかどうかが大きく変わってきます。
この記事では、用途地域とは何か?なぜ確認が必要なのか?をわかりやすく解説し、車庫選びの実務的なポイントまで行政書士が丁寧にご紹介します。
用途地域とは?
用途地域とは、都市計画法に基づき市街地の土地利用をコントロールするために、用途ごとに土地の使い方を制限するエリアのことです。
これは、住居や商業、工業などのエリアを適切に分け、混在を防ぐことで、住みよいまちづくりを目的としています。
現在、用途地域は以下の13種類に分けられています。
それぞれの地域には「建てられる建物」「用途」「規模」などに制限があり、運送業の営業所や車庫を置けるかどうかにも直結します。
なぜ用途地域の確認が必要なのか?
基本前提としては運送業の車庫は用途地域の制限はありません。
ただし、それは無蓋の車庫(いわゆる青空駐車場)の場合に限られます。
運送業の許可を取得する際には、「営業所」や「車庫」についての審査が行われます。
その中で、車庫の場所が用途地域に適合しているかどうかが大きな判断ポイントになります。
運送業の車庫は有蓋(屋根あり)か無蓋(屋根無し)かによって、設置できる条件が大きく変わります。
屋根のない車庫
無蓋の車庫(屋根のない車庫)の場合、用途地域による制限はありません。
基本的に、運送業の車庫で気をつけいないといけないのが「土地の地目項目」です。
運送業の土地の要件に関する地目項目については過去記事でも解説しています。

屋根のある車庫
運送業許可における有蓋の車庫(屋根がある車庫)には、倉庫内の車庫など建物内だけでなく、庇(ひさし)がついているだけでも有蓋の車庫という扱いになるので注意が必要です。
有蓋の車庫の場合、設置できない土地の条件が変わります。
この中で、「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」「第一種住居地域」「第二種住居地域」は建物が2階以下、広さが300㎡以下の車庫であれば有蓋の部分があって許可が下ります。
屋根の車庫の場合、設置できない車庫の条件が増えますので、専門の行政書士などのご相談されることをおすすめします。
まとめ
車庫の土地を確保してから、その土地が車庫の要件を満たさないとなってしまっては、資金も時間も無駄にしてしまいます。
今回は、都市計画法の用途地域にフォーカスし解説してきましたが、運送業の車庫で気をつけないといけいことには、土地ん地目項目などもあります。
運送業を開業したい・車庫の移転が必要という事業者様は、車庫の土地の候補地が決まった時点で、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめ致します。
行政書士に依頼するメリット
運送業の許可申請は、単なる書類作成だけでなく、法的要件や地域調整など高度な知識が必要です。
以下のようなメリットがあります。
- 要件に合った営業所・車庫選定のアドバイス
- 書類作成から提出代行まで一括サポート
- 不許可リスクを減らすための事前チェック
- 申請後の運輸局対応も任せられる
運送業の許可を取得するには、「土地の要件」「人の要件」「車両数の要件」など、いろいろな要件をクリアする必要があります。
法令に精通した行政書士がサポートすることにより、結果的にコストとリスクを最小限に抑えれることが可能です。
📞 初回相談無料!
まずはお気軽にお問い合わせください。
📍 対応エリア:大阪府
事業者様に変わり、煩雑な手続きを代行致します。